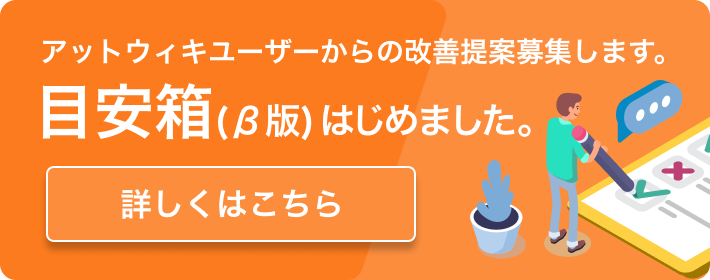LiarGirl
アイドルに興味を持ち始めたのはいつごろだろうか。
鮮明ではないが、なんとなく頭の中に残っている。
鮮明ではないが、なんとなく頭の中に残っている。
あれは、小学校の頃だったはずだ。
小さいころはゲームくらいしかやることがなかった覚えがある。
外で一緒に遊ぶようなことはなかった。
一緒に遊ぶような友達もいなかった。
引っ込み思案で、誰かに嫌われるのが怖くて、ずっと一人だった。
そんなある日だった、クラスの誰かがジュニアアイドルになるという話があった。
クラスの中の中心人物みたいな、可愛い女の子だった。
きらきらしてて、すごいなぁと思って見ていた。
小さいころはゲームくらいしかやることがなかった覚えがある。
外で一緒に遊ぶようなことはなかった。
一緒に遊ぶような友達もいなかった。
引っ込み思案で、誰かに嫌われるのが怖くて、ずっと一人だった。
そんなある日だった、クラスの誰かがジュニアアイドルになるという話があった。
クラスの中の中心人物みたいな、可愛い女の子だった。
きらきらしてて、すごいなぁと思って見ていた。
その日の夜、ご飯を食べながら点いていたテレビに少し目を向ける。
テレビでやっていたのは、よくある音楽番組であった。
毎週ゲストが登場し歌を歌っていく、普段なら気にもしなかっただろう。
テレビでやっていたのは、よくある音楽番組であった。
毎週ゲストが登場し歌を歌っていく、普段なら気にもしなかっただろう。
だが、そこで惹かれしまったのだ。
アイドルという、すごいキラキラしたものを。
自分もあんな舞台に立ってみたい、キラキラして、可愛く歌いたい。
アイドルという、すごいキラキラしたものを。
自分もあんな舞台に立ってみたい、キラキラして、可愛く歌いたい。
だが、アイドルになるなんて、無理だと思っていた。
杏奈は可愛いわけでも、ダンスがすごいわけでもない。
歌が好きだと言うだけで、アイドルとしてやっていける武器はない。
そして何より……この性格が一番の問題なのだ。
誰かと喋ろうとすると、いい言葉が出てこず喋れなくなる。
杏奈は可愛いわけでも、ダンスがすごいわけでもない。
歌が好きだと言うだけで、アイドルとしてやっていける武器はない。
そして何より……この性格が一番の問題なのだ。
誰かと喋ろうとすると、いい言葉が出てこず喋れなくなる。
そんな私に、アイドルなんて無理だったんだと諦めていたんだ。
その諦めた日から数年経ったあの日までは……あの人に会うまでは。
その諦めた日から数年経ったあの日までは……あの人に会うまでは。
「君さ……アイドルになる気はないか?」
道端で歌っている女性をぼーっとただ見ていた時だった。
自分の耳にはそんな声が届いた。
急すぎて最初は変な人かと勘違いした。
それはそうだ、自分みたいな人間にアイドルにならないかなんて急に声をかけてくるのだ。
普通に考えたら不審者とか、そういう風にしか見えない。
だけどその人は名刺を取り出して私に見せてくれたのだ。
自分の耳にはそんな声が届いた。
急すぎて最初は変な人かと勘違いした。
それはそうだ、自分みたいな人間にアイドルにならないかなんて急に声をかけてくるのだ。
普通に考えたら不審者とか、そういう風にしか見えない。
だけどその人は名刺を取り出して私に見せてくれたのだ。
765プロダクション、プロデューサー……765プロダクションという名前は少しは聞いたことがある。
諦めた日から、少しづつだがアイドルについては調べていた。
大手ではないが、少しづつ力をつけてきたプロダクションだと、どこかで見た覚えがある。
諦めた日から、少しづつだがアイドルについては調べていた。
大手ではないが、少しづつ力をつけてきたプロダクションだと、どこかで見た覚えがある。
「……でも、なんで……杏奈を?」
プロダクションの規模がどう、とかはどうだっていい。
何故、自分なんかに声をかけたのだろうか。
自分なんかより、そこで歌っている人の方が可愛いし、きらきらしているし、歌も上手い。
あの人をそっちのけで、こちらに声をかけている理由がわからない。
何故、自分なんかに声をかけたのだろうか。
自分なんかより、そこで歌っている人の方が可愛いし、きらきらしているし、歌も上手い。
あの人をそっちのけで、こちらに声をかけている理由がわからない。
「あ、杏奈ちゃんって言うんだね……えっと、君には、こう……説明できないけど、すごいものを感じるんだよ。
プロデューサーとしての勘、というと笑われるかもしれないけどさ……はは」
プロデューサーとしての勘、というと笑われるかもしれないけどさ……はは」
その笑顔から、望月杏奈は変わっていった。
ただ引っ込み思案だった彼女は、少しづつだが変わっていったのだ。
ただ引っ込み思案だった彼女は、少しづつだが変わっていったのだ。
☆ ☆ ☆
目を覚ますとそこは公園の中だった。
体が痛い、当然である、ベンチで眠っていたからだ。
ではどうして自分は公園のベンチで眠っていたのか。
横山奈緒は少しづつ自分の記憶を取り戻していく。
そして完全に思い出すころに、自分の置かれてる立場を嘆いた。
体が痛い、当然である、ベンチで眠っていたからだ。
ではどうして自分は公園のベンチで眠っていたのか。
横山奈緒は少しづつ自分の記憶を取り戻していく。
そして完全に思い出すころに、自分の置かれてる立場を嘆いた。
「家がなくなったとか家が燃えたから仕方なく、みたいなのやったらどれだけ良かったか……」
残念ながら、彼女の家がどうこうという問題ではない。
いや、むしろそちらの方がどれだけよかっただろうか。
まだそれだったならやり直しはいくらでも効くのだから。
いや、むしろそちらの方がどれだけよかっただろうか。
まだそれだったならやり直しはいくらでも効くのだから。
だが、今はそんな冗談も笑えない。
今まぎれもなく起きているのは、自身の命が係っている。
一歩間違えれば、お陀仏になる。
そんなふざけたような事を、仲間としろと?
今まぎれもなく起きているのは、自身の命が係っている。
一歩間違えれば、お陀仏になる。
そんなふざけたような事を、仲間としろと?
「プロデューサーさん……私はあんま頭良くないからわからへんけど……これだけは言えるわ」
「こんな殺し合いだなんて、どんな理由あるか知れへんけど」
「間違ってるやろ、こんな事……!」
「こんな殺し合いだなんて、どんな理由あるか知れへんけど」
「間違ってるやろ、こんな事……!」
ただ、今は歯噛みするしかなかった。
自分の首につけられているのは、あの爆発を巻き起こしたものと同じだ。
社長が殺された、あの瞬間を思い出す。
もし、何かしらがあり爆発させられればそこにあるのは……。
自分の首につけられているのは、あの爆発を巻き起こしたものと同じだ。
社長が殺された、あの瞬間を思い出す。
もし、何かしらがあり爆発させられればそこにあるのは……。
「……どないすればええねん」
自分一人では、どうすることもできない。
だが、他のメンバーがいれば何とかなるのではないのか?
しかしながら、もし誰かが殺し合いに乗っていたら?
今の自分など、格好の的であることは間違いないのだ。
だが、他のメンバーがいれば何とかなるのではないのか?
しかしながら、もし誰かが殺し合いに乗っていたら?
今の自分など、格好の的であることは間違いないのだ。
「……でも、信じなアカン……よね」
信じるしかないのだ、騙されるかもしれなくても。
信じれなくなって、誰も近くにいなくなるよりは。
信じれなくなって、誰も近くにいなくなるよりは。
「……よっしゃ! 空元気かもしれへんけど、やってやるで!
まずは誰か見つけんと始まらへんし!」
まずは誰か見つけんと始まらへんし!」
一人よりも二人、二人よりも三人、三人よりたくさん。
それくらい当然である、仲間が多いほどうれしいものはない。
まずは誰でもいい、一緒に行動してくれる人を探せばいい。
それくらい当然である、仲間が多いほどうれしいものはない。
まずは誰でもいい、一緒に行動してくれる人を探せばいい。
先ず隗より始めよ、かつての先人も言っていた。
大きなことを考えるより、身近な事から考えろ。
近場から行動していくのが最初である。
大きなことを考えるより、身近な事から考えろ。
近場から行動していくのが最初である。
「さーってと……まず近くを探さんとなぁ~……っと?」
そして探し始めてすぐだった。
彼女の目標は達成されることとなった。
見たことあるピンクのパーカーを着た紫色の髪の女の子が立っていた。
見たことないわけがない、あの姿は間違いなく知っている。
彼女の目標は達成されることとなった。
見たことあるピンクのパーカーを着た紫色の髪の女の子が立っていた。
見たことないわけがない、あの姿は間違いなく知っている。
「杏奈ぁあああああああああ!」
思わず走り出していた。
そして、思い切り抱きついた。
間違いなかった、この感触や匂いは間違いなく望月杏奈のものである。
そして、思い切り抱きついた。
間違いなかった、この感触や匂いは間違いなく望月杏奈のものである。
「良かったぁー! 無事やったんやな!」
「……奈緒さん」
「ん、どうしたんや杏奈! 感動の再開やで! もっとパーッと喜んだって……」
「……奈緒さん」
「ん、どうしたんや杏奈! 感動の再開やで! もっとパーッと喜んだって……」
ぐらり
視界が揺れた。
それと同時に違和感を感じた。
腹部に、何かが入ってくるような。
恐る恐る、自分の視界を下げる。
それと同時に違和感を感じた。
腹部に、何かが入ってくるような。
恐る恐る、自分の視界を下げる。
「――――え?」
あり得ない、そう思った。
何故、どうして、こんな事になっている。
私の腹に刺さっていた。
ナイフが、ぐっさりと、効果音がつくほど深く。
そのナイフを持つ手を、辿っていく。
何故、どうして、こんな事になっている。
私の腹に刺さっていた。
ナイフが、ぐっさりと、効果音がつくほど深く。
そのナイフを持つ手を、辿っていく。
「なん……で」
考えたくはなかった。
安心しきっていたのだ。
杏奈なら、大丈夫だと。
だが、違ったのだ。
それは自分の思い違いだった。
安心しきっていたのだ。
杏奈なら、大丈夫だと。
だが、違ったのだ。
それは自分の思い違いだった。
望月杏奈は、横山奈緒の腹を、刺していた。
☆ ☆ ☆
一体何をすればいいのか、まったくわからなかった。
気付いたら私はそこに立っていたのだ。
社長が目の前で爆破されて、死んだ。
ゲームの中でなら人が死ぬのを何度も見てきた。
だが、今ここにあるのは現実なんだ。
人は死んだら生き返ることはない。
気付いたら私はそこに立っていたのだ。
社長が目の前で爆破されて、死んだ。
ゲームの中でなら人が死ぬのを何度も見てきた。
だが、今ここにあるのは現実なんだ。
人は死んだら生き返ることはない。
「……怖い、よ」
今自分の首にあるのは、自分の命をいとも容易く奪ってしまう凶器だ。
外せる方法なんて、わかるわけもない。
なら、プロデューサーさんが言ったようにするしかないのだろうか。
外せる方法なんて、わかるわけもない。
なら、プロデューサーさんが言ったようにするしかないのだろうか。
『殺し合い』を、するしかない?
いやだ、そんなのはいやだ。
誰かを傷つけるのも、自分が傷つくのも、いやだ。
じゃあ、このまま何もしないでいるのか?
ここにいるみんながこのまま何もしなければ、いいのではないか?
信じている、信じたいけれど、もし……もしもの話だけれど。
誰かを傷つけるのも、自分が傷つくのも、いやだ。
じゃあ、このまま何もしないでいるのか?
ここにいるみんながこのまま何もしなければ、いいのではないか?
信じている、信じたいけれど、もし……もしもの話だけれど。
誰かが、殺し合いに乗ったかもしれない。
他の皆を殺して回っているかもしれない。
自分の後ろに――――いるかもしれない。
他の皆を殺して回っているかもしれない。
自分の後ろに――――いるかもしれない。
そう思うだけで、潰れそうになった。
ただでさえ弱い心がずたずたに、ぐちゃぐちゃに。
ただでさえ弱い心がずたずたに、ぐちゃぐちゃに。
「嫌だよ……プロデューサーさん……杏奈、どうすればいいの……?」
そして逃げる先は、プロデューサーさんだった。
私たちに殺し合いをするように仕向けた張本人だというのに。
それでもなお彼を信用してしまっているのだ。
悲しい事に一番信用していたのは、彼だったのだから。
私たちに殺し合いをするように仕向けた張本人だというのに。
それでもなお彼を信用してしまっているのだ。
悲しい事に一番信用していたのは、彼だったのだから。
そこで、先ほどの彼の言葉を思い出した。
――――『アイドル』として、最後まで諦めずに健闘してくれ。
この殺し合いは、アイドルとしてのお仕事なのだろうか。
そうだ、プロデューサーさんがそう言ったんだ。
だから私は、アイドルにならなくてはいけないんだ。
皆が待っていている、『アイドル』としての『望月杏奈』にならないといけないんだ。
――――『アイドル』として、最後まで諦めずに健闘してくれ。
この殺し合いは、アイドルとしてのお仕事なのだろうか。
そうだ、プロデューサーさんがそう言ったんだ。
だから私は、アイドルにならなくてはいけないんだ。
皆が待っていている、『アイドル』としての『望月杏奈』にならないといけないんだ。
この舞台≪殺し合い≫はステージなんだ。
アイドルがステージで輝かなくて、どうする。
怖がることはない、ここはステージなんだから。
『アイドル』にならなくてはいけない。
アイドルがステージで輝かなくて、どうする。
怖がることはない、ここはステージなんだから。
『アイドル』にならなくてはいけない。
「…………ビビッ! 杏奈、準備完了だよ!」
私はアイドルにはなれない。
その諦めを払拭してくれたのは、この私だったのだ。
練習して練習して創り出した、もう一人の『望月杏奈』だ。
何もできない本当の杏奈ではない。
アイドルとして研究されつくした、『望月杏奈』だ。
その諦めを払拭してくれたのは、この私だったのだ。
練習して練習して創り出した、もう一人の『望月杏奈』だ。
何もできない本当の杏奈ではない。
アイドルとして研究されつくした、『望月杏奈』だ。
「プロデューサーさんの言うとおり、皆を殺せばいいんだよね!
みんなを殺すのは心苦しいし悲しいけど、これも仕事だから!」
みんなを殺すのは心苦しいし悲しいけど、これも仕事だから!」
だが、望月杏奈はこの瞬間――――踏み間違えた。
『アイドル』という意味を。
『アイドル』という意味を。
☆ ☆ ☆
全て終わったのだ。
望月杏奈の目の前には、横山奈緒が転がっている。
まだ死んではいない、だが――――このまま放っておけば死ぬだろう。
ほら、もう血がこんなに出ているんだから。
助かるわけがない、死んでしまうんだ。
『ゲームオーバー』になるしかないのだ。
望月杏奈の目の前には、横山奈緒が転がっている。
まだ死んではいない、だが――――このまま放っておけば死ぬだろう。
ほら、もう血がこんなに出ているんだから。
助かるわけがない、死んでしまうんだ。
『ゲームオーバー』になるしかないのだ。
「奈緒さん……ごめんね、これも……アイドルとしてすべきことだから」
聞こえているかわからない。
それでも、彼女にはそう言っておきたかったのだ。
自分より年上なのに、付き合いやすかった。
仲良くしてくれた、お姉さんに対して。
微かながらも感じたのかもしれない。
『望月杏奈』本人としての、申し訳なさを。
許してもらえないのはわかっている。
自分がしているのは、最低最悪の行為なのだから。
これ以上ここにいると、アイドルになる魔法が解けてしまう。
プロデューサーさんが私にきっかけをくれて、編み出した魔法が解けてしまう。
ゲームでも、危ない事には近づかない方がいい。
ここから離れよう、そう思いながら歩き出した。
それでも、彼女にはそう言っておきたかったのだ。
自分より年上なのに、付き合いやすかった。
仲良くしてくれた、お姉さんに対して。
微かながらも感じたのかもしれない。
『望月杏奈』本人としての、申し訳なさを。
許してもらえないのはわかっている。
自分がしているのは、最低最悪の行為なのだから。
これ以上ここにいると、アイドルになる魔法が解けてしまう。
プロデューサーさんが私にきっかけをくれて、編み出した魔法が解けてしまう。
ゲームでも、危ない事には近づかない方がいい。
ここから離れよう、そう思いながら歩き出した。
――――その瞬間だった。
「……ま、って……杏奈……!」
現実はゲームのように上手くいかない。
望月杏奈の背後から聞こえてきた声。
苦しんでいるためだろう、多少声が震えていた。
だが、自分に対し真っ直ぐに刺さった。
望月杏奈の背後から聞こえてきた声。
苦しんでいるためだろう、多少声が震えていた。
だが、自分に対し真っ直ぐに刺さった。
「……奈緒、さん」
「なに、やってるんや……杏奈、こんなことして、喜ぶ、と」
「プロデューサーさんが、こうすることを祈ってるんだよ!?
だったら、期待に応えないと、そうしないと、また……」
「なに、やってるんや……杏奈、こんなことして、喜ぶ、と」
「プロデューサーさんが、こうすることを祈ってるんだよ!?
だったら、期待に応えないと、そうしないと、また……」
「ど阿呆!」
今までに、聞いたことない声だった。
どんな時でも笑って、他の人を励ましたりしてた横山奈緒とは違った。
明確な、『怒り』を持っていた。
どんな時でも笑って、他の人を励ましたりしてた横山奈緒とは違った。
明確な、『怒り』を持っていた。
「杏奈は何のために、アイドルをやってるんや……?
プロデューサーさんのためなん? 違うやろ……そうやないでしょ!?」
「……杏奈は、なんのため……に?」
プロデューサーさんのためなん? 違うやろ……そうやないでしょ!?」
「……杏奈は、なんのため……に?」
思考が揺らぐ、自分は何のためにアイドルをしている?
望月杏奈は何故アイドルになりたかったのか?
プロデューサーさんのため、ではない。
そうだ、そうなのだ。
わかった、思い出した。
アイドルになろうとした理由――――。
望月杏奈は何故アイドルになりたかったのか?
プロデューサーさんのため、ではない。
そうだ、そうなのだ。
わかった、思い出した。
アイドルになろうとした理由――――。
「杏奈は……キラキラしたステージで、皆を……幸せにしたかった……!」
「だったら、迷う事はないやろ……? 私の手を、取って……行くで、杏奈」
「奈緒さ――――」
「だったら、迷う事はないやろ……? 私の手を、取って……行くで、杏奈」
「奈緒さ――――」
――――パァン
その先は、遮断された。
たったひとつの、乾いた音が原因で。
たったひとつの、乾いた音が原因で。
「……え?」
横山奈緒の手が、望月杏奈に届くことは――――なかった。
差しのべられた手は、地に落ちる。
そして二度と、起き上がることはない。
差しのべられた手は、地に落ちる。
そして二度と、起き上がることはない。
「なん、で」
自分が刺した傷が原因、かと思った。
だが、違うのだ、明らかに違う。
さっきより、出血の勢いが増している。
急速な勢いで、横山奈緒の体を赤い海が沈めた。
だが、違うのだ、明らかに違う。
さっきより、出血の勢いが増している。
急速な勢いで、横山奈緒の体を赤い海が沈めた。
「……迷惑なのよね、進行が止まるって言うのは……それだけで厄介なのだから」
木の陰から、声がする。
やはりその声も聞いたことがあり、だからこそ信じたくなかった。
やはりその声も聞いたことがあり、だからこそ信じたくなかった。
「志保、ちゃん」
「…………」
「…………」
突然の再開は、最低だった。
【横山奈緒 死亡】
☆ ☆ ☆
私は、ある日プロデューサーさんに呼び出された。
何か用があるから、この時間にきてくれと言われた時間は、7時丁度だった。
こんな朝早くから呼び出すなんて、非常識もいい所だと思った。
まぁ、演技の練習で小学生メイドなどと言ったふざけたお題を出してくる人だ。
こういう非常識な所くらい付き合っていくうえで仕方ないと考えるしかなかった。
何か用があるから、この時間にきてくれと言われた時間は、7時丁度だった。
こんな朝早くから呼び出すなんて、非常識もいい所だと思った。
まぁ、演技の練習で小学生メイドなどと言ったふざけたお題を出してくる人だ。
こういう非常識な所くらい付き合っていくうえで仕方ないと考えるしかなかった。
「よう、志保……悪いなこんな時間に呼び出しちまって」
「いえ……何の用でしょうかプロデューサーさん、どうでもいい事なら数日は口をききませんよ?」
「いやいや、流石に何もなくてこんな時間に呼び出すわけないだろ」
「いえ……何の用でしょうかプロデューサーさん、どうでもいい事なら数日は口をききませんよ?」
「いやいや、流石に何もなくてこんな時間に呼び出すわけないだろ」
はっはっは、とプロデューサーさんは笑う。
別に私は面白くも何もないのだが。
別に私は面白くも何もないのだが。
だが、少し笑うと急にプロデューサーさんの顔が凍った。
少しだけだが、ドキッとした。
こう表現すると勘違いされそうだから追記しておくと、そういう色情的なものではない。
恐怖、そっちの方だと言っておこう。
あのプロデューサーさんが、こんな表情をしたのを見たことがなかったから。
ずっとどんな時も、笑って、泣いて、たまに変人で、感情豊かだったこの人が。
一切考えが読めない、そんな表情をしているのだから。
少しだけだが、ドキッとした。
こう表現すると勘違いされそうだから追記しておくと、そういう色情的なものではない。
恐怖、そっちの方だと言っておこう。
あのプロデューサーさんが、こんな表情をしたのを見たことがなかったから。
ずっとどんな時も、笑って、泣いて、たまに変人で、感情豊かだったこの人が。
一切考えが読めない、そんな表情をしているのだから。
「志保には、頼みたいことがあってな」
「――――なんでしょうか」
「お前はさ、演技の練習がしたいと言っていたよな?」
「言いましたね、今でもたまにつき合ってもらっていますが……それがどうかしましたか?」
「実はそんなお前にうってつけの仕事があってだな、受けるか? 受けないか?」
「そんな事、内容次第としか言いようがないですよ」
「――――なんでしょうか」
「お前はさ、演技の練習がしたいと言っていたよな?」
「言いましたね、今でもたまにつき合ってもらっていますが……それがどうかしましたか?」
「実はそんなお前にうってつけの仕事があってだな、受けるか? 受けないか?」
「そんな事、内容次第としか言いようがないですよ」
そういうと、またプロデューサーさんの表情が凍った。
何故だか、嫌な予感がした。
何か私に隠し事をしている、そんな印象が取れた。
何故だか、嫌な予感がした。
何か私に隠し事をしている、そんな印象が取れた。
「……そうか、そりゃあ内容次第だよな……うん」
「当然じゃないですか、もし何も知らずに受けて変な事をやらされそうになるなんてなったら、嫌ですから」
「当然じゃないですか、もし何も知らずに受けて変な事をやらされそうになるなんてなったら、嫌ですから」
当然のことだ、普段でもあまり信用できない部分が信用できない人なのだから。
こういう隠し事をして押し付けようという時に信用してはいけないのだ。
何をさせる気か情報を引き出すのは当然のことである。
この人がプロデューサーさんになってから大分経ち、どう扱えばよいかがわかるようになってきた。
こういう隠し事をして押し付けようという時に信用してはいけないのだ。
何をさせる気か情報を引き出すのは当然のことである。
この人がプロデューサーさんになってから大分経ち、どう扱えばよいかがわかるようになってきた。
「……んじゃ問答無用で言わせてもらおう……志保、お前は……人を殺す勇気があるか?」
何を言っているのかわからなかった。
人を殺す、何故そんなことをいきなり言っているのか。
そういう殺し屋みたいな役を仕事としてもらってきたという事だろうか。
人を殺す、何故そんなことをいきなり言っているのか。
そういう殺し屋みたいな役を仕事としてもらってきたという事だろうか。
「まったく意味がわからないです、それはどういう意図ですか」
「意図も何もないさ、言葉の意味だよ――――お前は人を殺せるか?」
「嫌ですね、そんな事で自分の人生を棒に振るほど私は馬鹿ではありません、というよりそれだけですか?
用がないのならやるべきこともあるので帰りますよ」
「意図も何もないさ、言葉の意味だよ――――お前は人を殺せるか?」
「嫌ですね、そんな事で自分の人生を棒に振るほど私は馬鹿ではありません、というよりそれだけですか?
用がないのならやるべきこともあるので帰りますよ」
振り返り、外に出ようとした時だった。
急に右肩を掴まれた、そしてそのまま壁に押し付けられる。
急に右肩を掴まれた、そしてそのまま壁に押し付けられる。
「……どういうつもりですかプロデューサーさん」
「ちゃんと話は最後まで聞くべきだと思うぜ、って事だよ……話はまだ終わってないんだよ」
「だったら茶化してないで言ってください、流石にふざけるのも度を越すと怒りますよ」
「ちゃんと話は最後まで聞くべきだと思うぜ、って事だよ……話はまだ終わってないんだよ」
「だったら茶化してないで言ってください、流石にふざけるのも度を越すと怒りますよ」
というより、すでに怒っている。
今までも茶化されたり遊ばれたりなんてことはあった。
だが、今回はいつもに増して悪質なのだ。
今までも茶化されたり遊ばれたりなんてことはあった。
だが、今回はいつもに増して悪質なのだ。
いや、これは違和感とでもいうのか。
プロデューサーさんの態度が、いつもよりおかしいのは明らかだ。
人を殺す勇気があるか、なんて不謹慎だし恐ろしい質問をしてる時点でおかしい。
プロデューサーさんの態度が、いつもよりおかしいのは明らかだ。
人を殺す勇気があるか、なんて不謹慎だし恐ろしい質問をしてる時点でおかしい。
しかも、さらなる問題点で言えばだ。
その質問がいつもの冗談に聞こえないのだ。
本当に人を殺せるか、見定めているような。
その質問がいつもの冗談に聞こえないのだ。
本当に人を殺せるか、見定めているような。
「……まぁ、もういいか……本題に入るぞ」
「やっと、ですか……でもふざけた内容だったら今度こそ帰りますよ」
「やっと、ですか……でもふざけた内容だったら今度こそ帰りますよ」
一応、釘を刺しておく。
これだけやっておいてどうでもいい事だったならば悪質にもほどがある。
しばらく無視するのも視野に入れなくてはならない。
そう思っていると、プロデューサーさんは口を開いた。
これだけやっておいてどうでもいい事だったならば悪質にもほどがある。
しばらく無視するのも視野に入れなくてはならない。
そう思っていると、プロデューサーさんは口を開いた。
「お前に、人を殺してほしい」
その言葉は、今までで一番意味不明で、でも……不安にさせられた。
☆ ☆ ☆
そして、今ここに立っているのは北沢志保≪きたざわしほ≫であり北沢志保≪アイドル≫ではない。
この殺し合いを進行する上での潜入員……プロデューサーさんが言うには『ジョーカー』とやらになった。
仕事は簡単、人を殺していくだけだ……同僚を殺していくだけだ。
この殺し合いを進行する上での潜入員……プロデューサーさんが言うには『ジョーカー』とやらになった。
仕事は簡単、人を殺していくだけだ……同僚を殺していくだけだ。
「志保……なんで、なんで……そんな……!」
「貴方だってやった事でしょう?」
「っ――――!」
「貴方だってやった事でしょう?」
「っ――――!」
そう、私は見ていたのだ。
先ほど横山奈緒に対して望月杏奈がナイフを使って刺殺しようとしたこと。
そして、それが未遂に終わった事を。
先ほど横山奈緒に対して望月杏奈がナイフを使って刺殺しようとしたこと。
そして、それが未遂に終わった事を。
挙句の果てには――――望月杏奈が更生しかけてしまった事を。
この殺し合いを進行する上で、殺し合いに乗った人がある程度いないといけない。
その一人として望月杏奈が行動してくれるのであれば喜んで放っておいただろう。
だが、横山奈緒が強かった、強すぎた。
一度アイドルとしての道を終わらせかけた望月杏奈を救おうとしたのだ。
自分を一度殺そうとしたのにもかかわらず。
その一人として望月杏奈が行動してくれるのであれば喜んで放っておいただろう。
だが、横山奈緒が強かった、強すぎた。
一度アイドルとしての道を終わらせかけた望月杏奈を救おうとしたのだ。
自分を一度殺そうとしたのにもかかわらず。
「大体、一度人を殺していて戻れるだなんて……そんな簡単な話にしていいんかしら?」
「違う……杏奈は、もうっ……!」
「プロデューサーさんのために動こうとした? それはあくまで言い訳じゃない……」
「違う、違う、違う……!」
「何が違うの? 貴方は殺そうとした、そして実際その一歩手前で行ってしまった」
「志保だって……奈緒さんを……殺し、た」
「私はもう、アイドルなんて諦めたもの……この殺し合いが始まった時から」
「……え?」
「違う……杏奈は、もうっ……!」
「プロデューサーさんのために動こうとした? それはあくまで言い訳じゃない……」
「違う、違う、違う……!」
「何が違うの? 貴方は殺そうとした、そして実際その一歩手前で行ってしまった」
「志保だって……奈緒さんを……殺し、た」
「私はもう、アイドルなんて諦めたもの……この殺し合いが始まった時から」
「……え?」
そう、私はすでにアイドル失格なのだ。
自分自身でそんなことわかっている。
だからこそ、容赦なく銃の引き金を引いた。
たった少し指先を動かすだけで、一人の命を動かしたのだ。
自分自身でそんなことわかっている。
だからこそ、容赦なく銃の引き金を引いた。
たった少し指先を動かすだけで、一人の命を動かしたのだ。
「私はもう、アイドルに戻れるとは思っていない……でも杏奈は、まだその幻想を追っている」
「……」
「誰かを笑顔にする、それがアイドルって言ったわよね」
「…………」
「でもあなたがした行為は違う、誰かを苦しめた」
「……もう、やめて……お願い、だから……!」
「……」
「誰かを笑顔にする、それがアイドルって言ったわよね」
「…………」
「でもあなたがした行為は違う、誰かを苦しめた」
「……もう、やめて……お願い、だから……!」
望月杏奈の精神がボロボロになっているのがわかった。
ただ、一つ引き金を引けばいい。
それで、終わらせることが出来るのだ。
ただ、一つ引き金を引けばいい。
それで、終わらせることが出来るのだ。
「そんな貴方が、アイドルを名乗る資格なんてないわ」
「……あ、ああ……あ、あ」
何かを喋ろうとした杏奈が、そのまま地面に倒れた。
過度のストレスは失神を引き起こすことがある、そう聞いたことがある。
彼女は今、自分に潰されたのだろう。
過度のストレスは失神を引き起こすことがある、そう聞いたことがある。
彼女は今、自分に潰されたのだろう。
本当なら、ここで殺してあげるべきだったのだろう。
その方が彼女は苦しまずに済むのだから。
その方が彼女は苦しまずに済むのだから。
「……まぁ、いいわ……このままにしても彼女はもう立ち直れない」
だが、殺さない。
彼女をあえて苦しませたかったからではない。
拳銃の引き金を引けなかったのだ。
銃の故障でもなんでもない、ただ……自分で彼女を殺したくなかった。
彼女をあえて苦しませたかったからではない。
拳銃の引き金を引けなかったのだ。
銃の故障でもなんでもない、ただ……自分で彼女を殺したくなかった。
横山奈緒を殺しておいて、なんてザマだとは思う。
だが……杏奈と自分があまりにも似ていたのだ。
全然違うが、似ているのだ。
狂っていてもなお、幻想を追おうとしている。
そして、自分とは違い、立ち直ろうとした。
そんな彼女が、眩しかった。
今ここで彼女を殺すことで、自分自身の微かな希望も殺そうとしてるように思えた。
だが……杏奈と自分があまりにも似ていたのだ。
全然違うが、似ているのだ。
狂っていてもなお、幻想を追おうとしている。
そして、自分とは違い、立ち直ろうとした。
そんな彼女が、眩しかった。
今ここで彼女を殺すことで、自分自身の微かな希望も殺そうとしてるように思えた。
プロデューサーさんを止めたい、そんな幻想を抱いてる自分を、殺すように思えてしまった。
もう引き金を引いてしまっている時点で、そんな幻想を抱くべきではない。
今自分が、杏奈に対して言ってしまったことがそのままブーメランのように自分に刺さる。
それくらい、わかっている――――でも
今自分が、杏奈に対して言ってしまったことがそのままブーメランのように自分に刺さる。
それくらい、わかっている――――でも
――――――――嘘をついてなくちゃ、思いがばれちゃう
☆ ☆ ☆
結局、私は公園から離れていた。
杏奈の傍にいてあげることはしないしできなかった。
プロデューサーさんに形は従っていることになっているのだ。
この殺し合いの円滑な進行をする事。
それが私の仕事である。
杏奈の傍にいてあげることはしないしできなかった。
プロデューサーさんに形は従っていることになっているのだ。
この殺し合いの円滑な進行をする事。
それが私の仕事である。
「……本当に」
何をやっているんだと思う。
こんなやりたくもない殺し合いを、しなくてはならないのか。
自分自身に嘘をついて、他人にも嘘をついて、戦っている。
こんなやりたくもない殺し合いを、しなくてはならないのか。
自分自身に嘘をついて、他人にも嘘をついて、戦っている。
ウソもホントウはね、つきたいわけじゃない。
私が貰った歌の歌詞だ。
まさに、その通りだと思った。
私を仲間と思ってくれたみんなを裏切り、殺そうとするなんて。
最低にもほどがある、最悪にもほどがある。
こんな姿を見たら、可奈は、静香は、どう思うだろうか。
杏奈は、私が壊してしまった。
可奈は……わからないけど、空元気に頑張っていると思う。
静香は……私以上に危険かもしれないし、プロデューサーさんに一矢報いようとしてるかもしれない。
他の皆も、動いているはずなのだ。
そんな中で私は……裏切った。
まさに、その通りだと思った。
私を仲間と思ってくれたみんなを裏切り、殺そうとするなんて。
最低にもほどがある、最悪にもほどがある。
こんな姿を見たら、可奈は、静香は、どう思うだろうか。
杏奈は、私が壊してしまった。
可奈は……わからないけど、空元気に頑張っていると思う。
静香は……私以上に危険かもしれないし、プロデューサーさんに一矢報いようとしてるかもしれない。
他の皆も、動いているはずなのだ。
そんな中で私は……裏切った。
「滑稽ね……私」
そうとしか言えなかった。
自分の事しか考えてなかったあの時と同じだ。
周りの事なんかどうでもいい、自分がするべきことをするだけ。
まさに、今の自分と同じだ。
自分の事しか考えてなかったあの時と同じだ。
周りの事なんかどうでもいい、自分がするべきことをするだけ。
まさに、今の自分と同じだ。
もうならないようにと考えていた過去と同じ運命を辿るなんて、とんだ哂い噺だ。
でも、私は動かねばならない。
この殺し合いを――――遂行するために。
でも、私は動かねばならない。
この殺し合いを――――遂行するために。
【一日目/朝/H-2】
【北沢志保】
[状態]ストレスによる軽度の体調不良
[装備]ベレッタM92(14/15)
[所持品]基本支給品一式、不明支給品0~1、9x19mmパラベラム弾入りマガジン(2)
[思考・行動]
基本:"ジョーカー"として動く
1:とにかく、人を殺して行く
2:嘘をついてなくちゃ――――
※ジョーカーとして訓練を受けているため拳銃などの扱いを把握しある程度の経験を持っています
【北沢志保】
[状態]ストレスによる軽度の体調不良
[装備]ベレッタM92(14/15)
[所持品]基本支給品一式、不明支給品0~1、9x19mmパラベラム弾入りマガジン(2)
[思考・行動]
基本:"ジョーカー"として動く
1:とにかく、人を殺して行く
2:嘘をついてなくちゃ――――
※ジョーカーとして訓練を受けているため拳銃などの扱いを把握しある程度の経験を持っています
【一日目/朝/H-2公園】
【望月杏奈】
[状態]気絶
[装備]バタフライナイフ(血液付着)
[所持品]基本支給品一式、不明支給品0~1
[思考・行動]
基本:――――
【望月杏奈】
[状態]気絶
[装備]バタフライナイフ(血液付着)
[所持品]基本支給品一式、不明支給品0~1
[思考・行動]
基本:――――
※横山奈緒の死体および支給品は放置されています
【バタフライナイフ】
望月杏奈に支給
片刃で広義のフォールディングナイフに属するナイフ
ブレードを上下からはさむように収納するのが特徴
望月杏奈に支給
片刃で広義のフォールディングナイフに属するナイフ
ブレードを上下からはさむように収納するのが特徴
【ベレッタM92】
北沢志保に支給
イタリアのピエトロ・ベレッタ社が生産・販売している自動拳銃
世界中の警察や軍隊で幅広く使われており、現在はコルト・ガバメントに代わりアメリカ軍の制式採用拳銃になっている
北沢志保に支給
イタリアのピエトロ・ベレッタ社が生産・販売している自動拳銃
世界中の警察や軍隊で幅広く使われており、現在はコルト・ガバメントに代わりアメリカ軍の制式採用拳銃になっている
| ♪魔法のアンサンブル | 時系列順に読む | Day dream believer |
|---|---|---|
| ♪魔法のアンサンブル | 投下順に読む | Day dream believer |
| GAME START! | 望月杏奈 | 最近、同僚のようすがちょっとおかしいんだが。 |
| GAME START! | 横山奈緒 | 死亡 |
| GAME START! | 北沢志保 | 三つのお願い |